
公開日2025.8.19
車だって夏バテする?! 愛車を守る猛暑対策ガイド
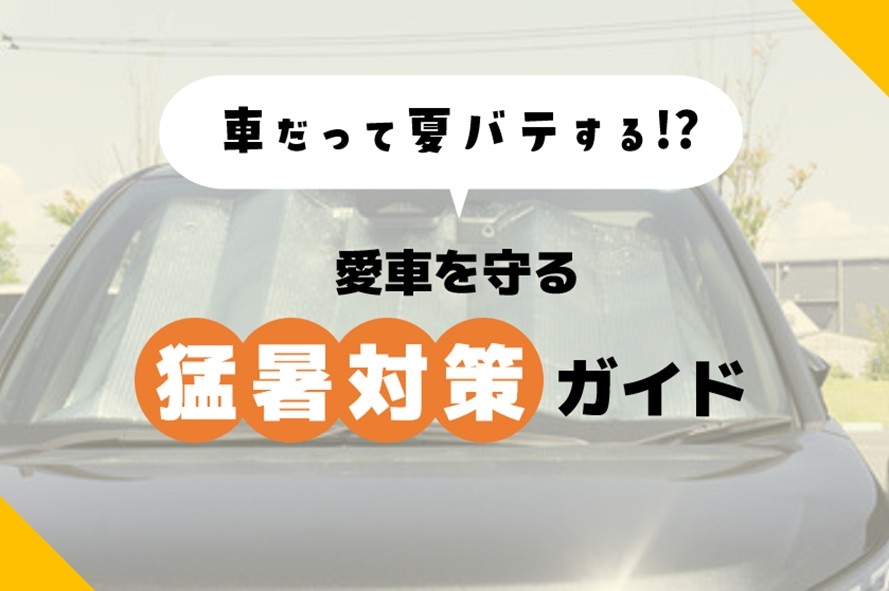
「夏バテ」と聞くと夏の暑さや湿度によって引き起こされる体調不良を思い浮かべる方も多いと思いますが、実は車にも暑さが原因で不調が起こることがあります。
今回は車の夏バテとその対処法について解説します。
車の「夏バテ」とは?
猛暑の中での過酷な走行や、連日の高温状態が続くと、エンジンや駆動系、電装系などにさまざまなトラブルが発生しやすくなります。
具体的には以下のような症状が挙げられます。
1. オーバーヒート(冷却不足)

クルマは、エンジンの熱を冷却水で下げ、それによって熱くなった冷却水をラジエーターに送り、走行風やファンで冷やすという水冷方式が使われています。
夏場など極端な暑さでは、ラジエーターや冷却水が本来の性能を発揮できず、エンジン温度が異常に上昇することでオーバーヒートを引き起こすことがあります。
オーバーヒートが起こると、エンジン警告灯が点灯しますが、そのまま走行を続けてしまうとエンストの原因となるほか、最悪の場合はエンジン交換につながる可能性があります。
2. バッテリー性能低下
夏の運転に欠かせないのがエアコンです。
エアコン使用時は電力消費が通常時と比べて多くなるため、バッテリーに負担がかかります。
また、渋滞時はさらにバッテリー負担が大きくなるため、長期連休などでお出かけの際に渋滞に巻き込まれるとバッテリーに大きな負担がかかります。
バッテリーの性能が低下すると、エンジンがかかりにくくなったり、パワーウインドウの上下動が遅く感じられたり、ライトやナビ、室内灯の調子が悪く、暗く感じられるようになることもあります。
バッテリー上がりにも繋がるため、注意が必要です。
3. タイヤの空気圧変動

気温が高いとタイヤの中の空気が膨らみ、空気圧が上がりすぎることがあります。
空気圧が高すぎると、燃費が悪くなるたけでなく、バーストの危険性があるため特に注意が必要です。
また、夏場はアスファルトが高温になることから、摩擦熱からパンクやバーストを引き起こしやすいでしょう。
偏ったすり減りやタイヤの劣化があると、バーストの危険性はより高まります。
4. エアコン回路の負担増大
エアコンを長く使い続けると、部品の負担が増えたり冷媒が減ったりして、冷えが悪くなることがあります。
その分燃費も落ちやすくなり、エンジンにかかる負荷も大きくなってしまいます。
5. オイル劣化・流動性低下
エンジンオイルの油温が高い状態が続くと、オイルの粘度が低く流れにくくなってしまうため、エンジンオイルの働きが低下します。
潤滑がうまくいかず、エンジンの金属部分がすり減り、ギアの動きに不具合が出るおそれがあります。
また、エンジンオイルが規定量よりも少ない状態で乗ってしまうと、エンジンオイルの温度が上昇しやすく、トラブルの原因に繋がることもあります。
夏本番前に必ずチェック!基本の「サマーメンテナンス」
車の夏バテはメンテナンスを施すことで防ぐことができます。
ここからは、猛暑を乗り切るための車のサマーメンテナンスについて解説します。
冷却系統の点検・整備

冷却系統については以下の項目を点検・整備しましょう。
冷却水(LLC)量と凍結防止剤濃度の確認
冷却水はウォーターポンプ→ラジエーター→エンジンへと循環し、熱を逃がす要です。
蒸発や漏れで減っている場合は規定量まで補充し、冷却水の凍結防止/防錆剤濃度もメーカー指定値を守りましょう。
ラジエーターキャップやホースの劣化チェック
内圧を一定に保つラジエーターキャップ、経年劣化しやすいホースに亀裂や膨張がないか点検しましょう。
高温下での破損リスクを未然に防ぎます。
電動ファン・ベルト類の動作確認
電動ファンが適切に作動するか、水温センサーの配線状態やベルトの張りも確認しましょう。
ベルトの摩耗や緩みは、ファンの駆動力不足を招くため注意が必要です。
バッテリーと充電系のチェック

次にバッテリーと充電系のチェックポイントを解説します。
バッテリー端子の腐食除去と締め付け
ターミナル部に白い粉が付着していないかを点検し、専用ブラシで清掃します。
腐食を除去することにより、接触不良による電圧降下を防ぎます。
バッテリー電圧の測定
エンジン停止時に12.4V以上、アイドリング中に13.8〜14.4Vを維持しているかテスターで確認しましょう。
夏場は特に劣化が進みやすいため、2年以上使ったバッテリーは早めの交換を検討してください。
タイヤの空気圧・外観点検

タイヤの点検も欠かさずにチェックしてみてください。
空気圧の調整
朝一番の冷えた状態で指定空気圧をチェック。
気温が上がると数%プラスされるため、やや低めに調整しておくと最適値に近づきます。
タイヤの残溝・損傷確認
残りミゾが3mm以下、またはサイドウォールに異常がないかを確認します。
ひび割れやコブがあると高温下でバーストしやすくなるため注意が必要です。
オイル・フルード類の交換・補充
定期的なメンテナンスを欠かさず受けておくことが、オイル・フィールド類の状態を良好に保つコツです。
エンジンオイルのレベルと粘度状態
冷間時にレベルゲージでチェックし、汚れや乳化があれば早めに交換してください。
夏場は高温用に指定された粘度(例:0W-20→5W-30)への変更も検討してみましょう。
ATF・CVTフルードの点検
オイルの汚れ具合やレベルを点検します。
交換サイクルがモデルによって異なるため、整備スケジュールに従ってディーラーや指定の整備工場へ依頼してください。
ブレーキ・パワステフルード
汚れや水分混入は制動力低下・操舵感の悪化を招くため、メーカー推奨周期での交換を推奨します。
走行中に気をつけたい「夏バテ予防ドライブ術」

暑い日のドライブは、走行中にもできる対策はあるのでしょうか。
ここからは真夏の車のトラブルを減らすためのドライブ術をご紹介します。
エンジン始動後はアイドリングを短時間
エンジン始動直後はオイルが十分に回っていないため、急加速や高回転は厳禁です。
冷却系の温度が低温の状態であるため、軽く油圧が安定する数十秒のアイドリングをおすすめします。
渋滞・信号待ちではエアコンの使い方に配慮
渋滞時はコンデンサーの冷却風が減少し、エアコン効率が落ちがちです。
風量を「強→中」に落としつつ、窓を数センチ開けて外気を取り込むと内外温度差が緩和し燃費悪化を防ぎます。
高速巡航時はレーダークルーズコントロールを活用
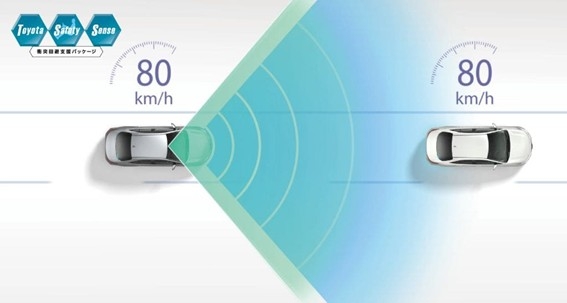
一定速度走行はエンジン負荷・燃費ともに効率的です。
高速道路ではレーダークルーズコントロールを使い、省燃費運転とドライバーの疲労軽減を同時に図りましょう。
こまめな休憩とボンネット確認
長距離ドライブ時は2時間ごとに休憩を取り、ボンネットをあけてラジエーター周辺の異常(蒸気・漏れ)を視認しましょう。
エンジンルームの高温状態をリセットし、オーバーヒート予防につながります。
突然のトラブル時の応急対処法

もしトラブルが起こってしまった際にはどのように対処したらよいのでしょうか。
万一のために知っておくと安心な応急対処法を解説します。
オーバーヒート警告が出たら即停車
オーバーヒート警告が出たら、周囲の安全を確認したうえで、まず車を他の車の邪魔にならない安全な場所に停め、走行を続けないようにしてください。
エンジンは止めずに、そのままかけておくようにしましょう。
ボンネットを開けて冷却状況を確認しましょう。
熱いラジエーターには素手で触れず、しばらく放置してからリザーブタンクへ冷却水を補充します。
ただし、このとき冷却ファンが回っていなかったり、冷却水が漏れてたりする場合は、エンジンを止めて自然冷却するようにしましょう。
可能であれば再度エンジンをかけるのではなく、速やかに救護を呼びディーラーや整備工場に持ち込むことをおすすめします。
バッテリー上がり

車のバッテリーが上がった場合、まずはライトや電装品をすべてOFFにし、ジャンピングスタートで応急対応します。
ジャンピングスタートには専用のブースターケーブルを使い、救援車のバッテリーと接続します。
赤いケーブルは+端子同士、黒いケーブルは救援車の-端子から上がった車のエンジンなどの金属部分に接続します。
ケーブルがつながったら、救援車のエンジンをかけ、AT車であればパーキング、MT車であればニュートラルの状態でサイドブレーキをかけます。
数分後に上がった車のエンジンを始動し、ケーブルを接続時と逆の順番で取り外します。
その後は30分以上走行またはアイドリングで充電を促します。
原因がバッテリー劣化によるものであれば、エンジンを止めると再び始動できない場合も考えられます。
いずれの場合も、速やかにディーラーや整備工場で点検してもらい、必要であればバッテリーの交換をしましょう。
タイヤバースト
タイヤがバーストしたらスペアタイヤへの交換が必要です。
まずは冷静に車のコントロールを保ち、安全な場所へ停車させましょう。
停車したら、他のドライバーへの注意を促すため、警告灯を点灯させてください。
タイヤの交換に際し、ジャッキアップを行うときは必ず平坦な場所を選びましょう。
必要に応じてロードサービスを利用することも検討するとよいでしょう。
愛車を「夏バテ」から守るために
今回は車の夏バテと対処法について解説しました。
愛車の健康管理は、安全運転・快適ドライブの基本です。
長期連休の前は車の点検を行ったうえで快適なドライブを楽しんでください。
トヨタモビリティ神奈川の公式Youtubeでは、クルマに関する様々な情報やドライブが快適になるような豆知識をご紹介しています。
ぜひ合わせてチェックしてみてください。
公式Youtubeはこちらから▼こちらの記事もCHECK!


