
公開日2024.12.09
新車タイヤの交換時期は何年?目安や長持ちさせる方法を紹介!
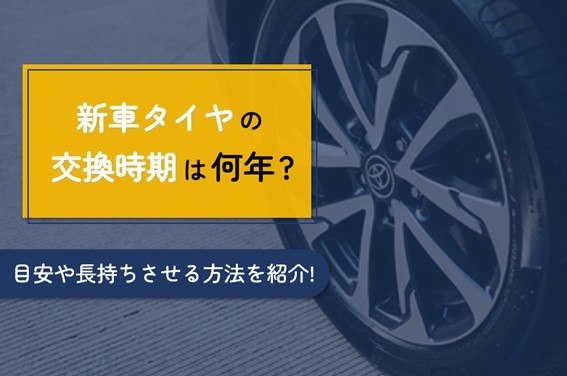
タイヤは走行しているうちに徐々にすり減っていきますが、どのくらいで交換が必要なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回はタイヤの交換時期の目安や判断基準、タイヤを長持ちさせる方法について解説していきます。
タイヤの交換時期はどのくらい?目安や判断基準を5つ紹介!
タイヤは走行するだけでなく、荷重を支え路面からのショックを吸収するといった役割も担っています。
タイヤは走行時の動作や衝撃を吸収することにより、少しずつ摩耗していきますが、摩耗したタイヤを使用し続けることは、スリップしやすくなるため危険です。
場合によってはタイヤがバースト(破裂)する恐れもあり、安全な走行ができなくなります。
安全な走行を維持するためにも、まずはタイヤの交換時期の目安について解説していきます。
使用年数

タイヤの側面には製造年度が記載されており、製造年度から使用年数を確認できます。
一般的にタイヤ交換の目安は4~5年程度と言われており、ゴム製品は製造から4~5年経過すると硬くなり、ひび割れを起こしやすくなります。
タイヤのひび割れはパンクや破裂の原因になりうるため、走行距離が短い場合でも4〜5年が経っていれば点検を行ない、必要であれば交換しましょう。
特にひび割れたタイヤで高速道路を走行するとバーストの危険性が高まるため注意が必要です。
走行距離

タイヤは残りの溝の深さが1.6mmになると、「スリップサイン」マークが現れます。
新品のタイヤの溝の深さの平均値は約8mmで、一般的なタイヤの場合5,000kmの走行で1mmタイヤが摩耗するため、約32,000kmでスリップサインが出現する計算です。
スリップサインはタイヤの使用限度で、1箇所でもスリップサインが出ると、そのタイヤは使用してはいけないと法律で定められています。
安全な走行のためには、走行距離30,000kmを超えてきたら使用限度が近づいていると考えましょう。
タイヤの溝

タイヤの状態によっては、使用年数や走行距離が目安に達していなくても、タイヤの溝が浅くなっているケースがあります。
先述の通り、タイヤの溝の深さが1.6mmになるとスリップサインが出現し使用できなくなります。
注意しておきたいのが、1.6mmというのは限界を表す数値のため、それまでは安全に走れると保証する数値ではありません。
夏用タイヤは4mm、冬用タイヤは5mm以下になるとブレーキの効きが悪くなり始めるということも覚えておくと便利です。
ご自身で出来る!タイヤの溝をセルフチェックする方法
タイヤの溝の深さをご自身でチェックしたい場合、100円玉を使うと簡単にチェックすることができます。
100円玉は縁から「1」の左側までが約5mmのため、100円玉をタイヤの溝に当て、1が隠れている場合は5mm以上だと判断できます。
逆に1が丸見えの状態だと5mm未満ということになり、交換の目安となります。
お出かけ前などご自身でチェックしておきたいシーンで覚えておくと便利です。
ただし、あくまでもこちらは簡易的なチェック方法のため、安全に乗り続けるためには定期的にディーラーで確認してもらうようにしましょう。
タイヤの溝が浅くなるとどうなる?
タイヤの溝が浅くなると、どのくらい制動距離に影響が出るのでしょうか。
1,800ccの乗用車で、タイヤサイズは165SR13、空気圧は170Kpaに揃え、アスファルト湿潤の路面で時速80km/hで制動距離を測った場合、新品タイヤは約45m、残り溝の深さが1.6mmまですり減ったタイヤでは約54mという結果になりました。
その差は約9メートルもあり、タイヤの溝がブレーキの効き具合を大きく左右していることがわかります。
また、タイヤの性能低下が原因で起こりうる現象として「ハイドロブレーニング現象」があります。
ハイドロプレーニング現象とは雨天時などに濡れた路面を高速で走行した際に、タイヤと路面の間に水膜ができ、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象です。
スピードの出し過ぎも原因の1つですが、タイヤ溝の過度な摩耗や空気圧の不足によっても発生しやすくなります。
ハイドロプレーニング現象が起こるリスクを減らすためにも、タイヤの残り溝をチェックしてみてください。
傷・ひび割れ

タイヤに傷やひび割れが見られたら交換時期です。
走行前に、タイヤに切り傷や擦り傷、ひび割れ、溝部の裂けなどがないか目視しましょう。
傷やひび割れは経年劣化によるものだけでなく、釘やガラス片などの異物が刺さったり、縁石に接触したりすることでも起こりやすいです。
また、タイヤはゴム製品のため、あまり走行していなくても経年劣化します。
久しぶりに車を使用する際などは、お出かけ前にタイヤの状態をチェックすることをおすすめします。
さらに、ゴム製品は熱の影響を受けやすいため、路面温度が高い夏に劣化が進みやすいことも留意しておきましょう。
偏摩耗

タイヤが一部分だけ偏ってすり減っている状態を偏摩耗といいます。
他の箇所と比べて特定の場所の溝が浅いと、走行中の振動や騒音の原因となります。
また、偏摩耗の部分からタイヤが破裂することもあるため、タイヤに偏摩耗がある状態で走行を続けると大変危険です。
全体的にみるとそれほど溝が摩耗していなくても、偏摩耗から交換が必要になる場合があります。
タイヤを長持ちさせる方法
タイヤは日常的な心がけで長持ちさせることができます。
ここからはタイヤを長持ちさせるための方法を解説していきます。
タイヤの空気圧を定期点検する

タイヤの空気圧は自然に低下するため、月に1回程度、タイヤの空気圧を点検するのがおすすめです。
空気圧不足での走行はパンクの原因となり、事故のリスクも高まります。
逆に、空気圧を保つことでタイヤの偏摩耗を防げるため、空気圧の調整はタイヤを長持ちさせるために必要不可欠です。
空気圧は車種によって異なりますが、運転席のドア付近に適正空気圧を記した表示シールが貼られているため、ぜひ一度ご自身の愛車を確認してみてください。
また、ご自身で判断が不安な方は、ディーラーやカー用品店などでタイヤの空気圧をチェックしてもらいましょう。
タイヤの位置をローテーションする

全体的なタイヤの寿命を延ばすため、定期的にタイヤの位置をローテーションするのもおすすめです。
例えば、エンジンが前にあるFF車では、後輪よりも前輪の摩耗が早い傾向にあります。
タイヤを同じ位置のまま使い続けると、4本のタイヤで摩耗の進み具合が異なるため、偏摩耗につながる可能性もあります。
入れ替えのタイミングやどのように入れ替えると効果的なのかは、車の使い方や駆動方式で異なるため、メンテナンスの際などに相談して確かめてみましょう。
運転方法を工夫する

運転方法によってもタイヤの摩耗の速度が異なるため、日頃の運転を工夫することも大切です。
例えば、急ブレーキや急ハンドルはタイヤの寿命を縮めるためおすすめできません。
車が停まった状態でハンドルを切るのもタイヤに負担をかけることになります。
また、段差を乗り越える必要があるときにはゆっくりと車を操作するなど、タイヤに優しい運転を心がけるようにしましょう。
タイヤの点検、適切な時期での交換で安全なカーライフを!
今回はタイヤの交換時期の目安や長持ちさせる方法などについて解説しました。
トヨタモビリティ神奈川では車検以外に、法定12ヶ月点検やプロケア10(6ヶ月点検)などの点検サービスを行なっています。
トヨタ車はもちろんのこと、トヨタ以外の国産メーカー車の車検・点検も行なっておりますので、すでに車をお持ちの方やこれから車を購入予定の方はぜひご相談ください。
新車の購入や車の選び方について、オンラインでの相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
オンライン購入相談はこちらから▼この記事を読んだあなたにおすすめ


