クラウン通がかよう 「ひゃくばん倶楽部」 第十二話 : 安全・安心の歴史
2018.07.18
「ひゃくばん倶楽部」へようこそ。私の名前は「ひゃくばん」。
この「ひゃくばん倶楽部」の案内人。一般的には、初代クラウンと呼ばれている。
1962年に発売された2代目クラウンは、私(初代クラウン)より全長が200mmも長くなり、当時、世界的な流行となったフラットデッキスタイルが採用され、ずいぶんモダンなスタイルになった。
この時にはスタイルだけではなく、国産初の安全合わせガラスや室内全体に配置されたセーフティ・パッドによって安全性も確保された。
まさに、ハイウェイ時代にふさわしい、安全なクルマの誕生だった。
6月26日に発売された15代目新型クラウンにも、人とクルマがふれあう全てのステージにおいて、安全をサポートする最先端技術が導入されている。
第9話では、駐車場におけるサポートブレーキ“インテリジェントクリアランスソナー”などについて話したが、今日は走行中のサポートブレーキについて話をしよう。
今までに車の運転をしていて人や自転車が飛び出してきて“ヒヤリ”とした経験はないだろうか?
そんな“ヒヤリ”をサポートしてくれるのが、この15代目新型クラウンの全グレードに標準装備された“プリクラッシュセーフティ”だ。
夜間の歩行者も検知してくれるプリクラッシュセーフティには、走行中の前方を見守る“2つのセンサー”が搭載されており、衝突の危険を検知すると、先ずは“ブザーとディスプレイ表示”でドライバーに注意を喚起してくれる。
ブレーキを踏めた場合にはプリクラッシュブレーキアシストが作動。踏めなかった場合にはプリクラッシュブレーキが作動して衝突を回避またはダメージの軽減をはかってくれる。
2つのセンサーとは、クルマの先端にあるクラウンのエンブレム周辺に搭載された“ミリ波レーダー”と、フロントウインドウの内側に搭載された“単眼カメラ”である。
ミリ波レーダーは、遠方まで精度よく距離を検出でき、夜間や雨天などの影響も受けにくい。一方、形状認識は不得意である。
単眼カメラは、形状認識が得意で、先行車や歩行者を認識できるが、天候や夜間、逆光の影響を受けやすい。
2つのセンサーは、互いの長所を活かし短所を補いあう、まるで人間のようなシステムなのだ。
ただ、システムが優秀だからといって頼りすぎたり過信しすぎたりするのは良くない。
運転者には安全運転の義務があり、自らの操作で安全を確保することは忘れないでもらいたい。
人間とシステムが協力して事故を減らす…あの頃の私はこんな時代がくるとは夢にも思わなかった。
先進の安全・安心機能を搭載したクラウンを、ぜひお近くの神奈川トヨタで確かめて欲しい。
それではまた、「ひゃくばん倶楽部」で逢おう。
■どうして私が、「ひゃくばん」と呼ばれているのか…ご存知ない方は「ひゃくばん物語」をご覧いただきたい。
【ひゃくばん物語】
私の名前は“ひゃくばん”。1955(昭和30)年生まれの63歳。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
「博物館でしかお目にかかれない」などという人もいるが、私は今でも地面さえあれば何処へでも走っていける。
もちろん、こうして今も元気に走り続けていられるのには理由がある…続きを読む
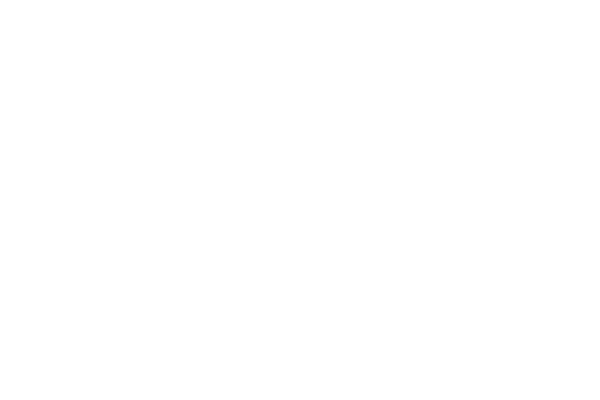
クラウン通がかよう 「ひゃくばん倶楽部」 第十一話 : 走行安定性の歴史
2018.07.14
「ひゃくばん倶楽部」へようこそ。私の名前は「ひゃくばん」。
この「ひゃくばん倶楽部」の案内人。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
今日は、クラウンの走行安定性へのこだわりについて話をしよう。
「美しいデザインは機能をあらわす」と言われた2代目クラウンのフラットデッキスタイル★1は、単にモダンなデザインという見た目の問題にとどまらなかった。
低重心で空気抵抗の少ないボディは、走行安定性の向上にもつながっていたのだ。
はしご型フレームだった私(初代クラウン)に対し、2代目にはX型フレームが採用され、耐久性も大幅に向上した。
潤滑、冷却機構も改良され、ハイウェイ時代の到来にも対応した最先端のクルマだった。
★1.フラットデッキスタイル=ボンネットとトランク面がフラットなデザイン。
2018年6月26日に発売された15代目新型クラウンは、TNGA★2に基づきプラットフォームを一新。
クルマの本質である走りの楽しさを磨くべく、地球上で最も過酷と称されるニュルブルクリンク★3を走りこみ、どんな路面変化でも目線がぶれない新次元の走行安定性が体感できる、レーシングドライバーもワクワクするクルマに仕上がっている。
★2.TNGA=TOYOTA New Global Architecture、トヨタが取り組む次世代プラットフォームを基幹としたクルマづくりの構造改革の総称。
★3.ニュルブルクリンク(北コース:ノルドシュライフェ)=Nurburgring-Nordschleife、超高速から低速まで多種多様な170以上ものコーナーが続き、高低差300mと起伏が激しく、路面もうねりを伴う。このような過酷な道が20.8kmも続くニュルブルクリンクは「車両開発の聖地」とも呼ばれ、世界の自動車メーカーがクルマを鍛えるために集まる。
世界のクルマが切磋琢磨する車両開発の聖地を走りこんだ新型クラウンの実力を、ぜひお近くの神奈川トヨタで確かめて欲しい。
それではまた、「ひゃくばん倶楽部」で逢おう。
■どうして私が、「ひゃくばん」と呼ばれているのか…ご存知ない方は「ひゃくばん物語」をご覧いただきたい。
【ひゃくばん物語】
私の名前は“ひゃくばん”。1955(昭和30)年生まれの63歳。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
「博物館でしかお目にかかれない」などという人もいるが、私は今でも地面さえあれば何処へでも走っていける。
もちろん、こうして今も元気に走り続けていられるのには理由がある…続きを読む
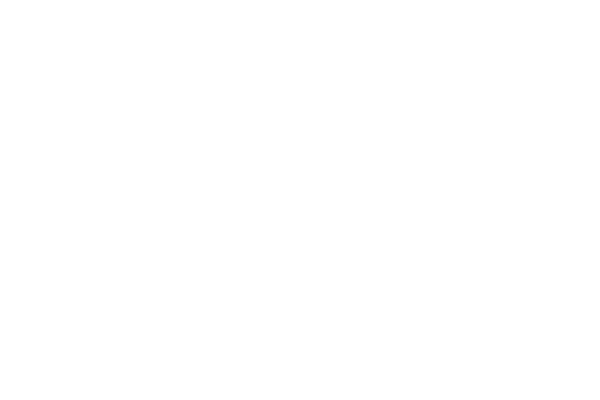
クラウン通がかよう 「ひゃくばん倶楽部」 第十話 : 快適と安全Ⅱ
2018.07.12
「ひゃくばん倶楽部」へようこそ、私の名前は「ひゃくばん」。
この「ひゃくばん倶楽部」の案内人。一般的には、初代クラウンと呼ばれている。
私達(初代クラウン)が競った三浦半島一周ラリーから約60年。
トヨタの“TS050HYBRID”が、世界3大レースのひとつ「ル・マン」を制した。
このモンスターマシンを1.2フィニッシュさせた、ドライバーは、この“TS050HYBRID”を「乗り心地が良い」「気持ち良く運転できる」と語っている。
24時間走りつづける過酷なレースにおいて、ドライバーが運転を楽しめる「心地よさ」や「気持ちよさ」は大切な事だ。
では、その「心地よさ」や「気持ちよさ」は、どこから来るのだろう。
そのひとつに、「つながる力」があると私は思っている。
“TS050HYBRID”は、最先端のハイブリッドカーであると同時に、最先端のコネクティッドカーでもある。
「ル・マン」参戦直前のインタビューで、2人のドライバーがあるレース中のエピソードを語っている。
異国の地にいるトヨタの社長が、レース中のドライバーを気遣ってクルーに連絡を入れた。
するとその言葉はクルーを介して、リアルタイムにドライバーに伝えられた。
届いたのは「気持ち」だった。
つながっているのは肉声ばかりではない。通信機器を通して、クルーは常にマシンの状態を把握している。
マシンのどの部分に異常が発生しているのか、何が限界を迎えそうなのか、ピットインが必要なのか、まだ走れるのか…。
それらを全て把握しているから最善のタイミングでピットインができるし、交換部品も用意できており、クルーも何をすれば良いかを事前に把握しているのでロスがない。
ドライバーは、いつも優秀なクルーに見守られている安心感があるのだ。
やはり、「ル・マン」を制覇したモンスターマシンは凄いの一言に尽きる。
実はこの技術が15代目の新型クラウンにも応用されているのをご存知だろうか。
コネックティッドカー・クラウンがもたらす、クルマと人の新しい関係を、是非、お近くの神奈川トヨタで体験してほしい。
それではまた、「ひゃくばん倶楽部」で逢おう。
■どうして私が、「ひゃくばん」と呼ばれているのか…ご存知ない方は「ひゃくばん物語」をご覧いただきたい。
【ひゃくばん物語】
私の名前は“ひゃくばん”。1955(昭和30)年生まれの63歳。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
「博物館でしかお目にかかれない」などという人もいるが、私は今でも地面さえあれば何処へでも走っていける。
もちろん、こうして今も元気に走り続けていられるのには理由がある…続きを読む
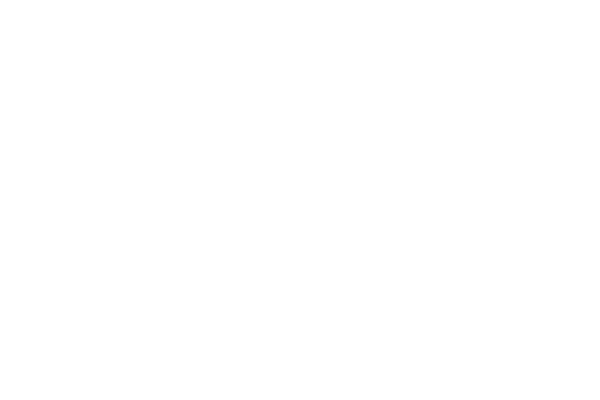
タクシー会社で ユニバーサルエスコートマナー講習
2018.07.11
「ありがとう、またお願いね!」そんな言葉をいただけたら、毎日の仕事がとても楽しくなります。
そして、そんな言葉をいただける乗務員の方が増えれば、職場の未来も明るいはず!
人生100年時代。私たちの街には様々な方が暮らし、様々な活動をしています。移動に車イスが必要な方もいらっしゃるでしょう。
そんな方にとって、タクシーは欠かせない乗り物なのです。
「車イスを使われているお客様への対応をどうすればいいのか…」という不安のためにご用意したのがこのプログラム。
7月4・5日の2日間、神奈川トヨタは、川崎交通産業株式会社様で乗務員の方々を対象に「ユニバーサルエスコートマナー講習」を実施しました。
まずは講師が「車イスって、どういう方が利用されると思いますか?」と、問いかけると色々な答えが返ってきました。
私たちがお伝えしたかったのは、車イスを利用されている方に対して専門的な知識や技能、そして特別な用具が無くても立派にサポートができる、ということです。
とはいえ、車イスからタクシーに乗り換えるには、シートへの移乗が必要です。
車イスをご利用の方にとって、サポートがあると嬉しい場面です。
まずは、目線をあわせて笑顔でお声掛けをしてお客様に合ったサポートを提供していくことが大切です。
例えば、立ち上がる時には「手をお貸しいたしましょうか?」や「腕にお掴まりください」など、乗務員の腕や肩も立派なサポート用具になります。
タクシーのドアも窓を開けて動かないように支えておけば、お客様が手すりがわりにも利用できるのです。
この日行った講習は、30分の短い講習でしたので、全てを身につけることはできませんが、専門的な知識や技能、特別な用具を使わなくても、実践できる事はたくさんあります。
ひとつ一つは些細なことでも、その積み重ねによってお客様の「ありがとう」につながっていくことが乗務員の方々へのモチベーションの向上にもなります。
私たちも「ありがとう、またお願いね!」と、言っていただける講習会を続けていき、明るい未来に貢献できるよう頑張っていきます!
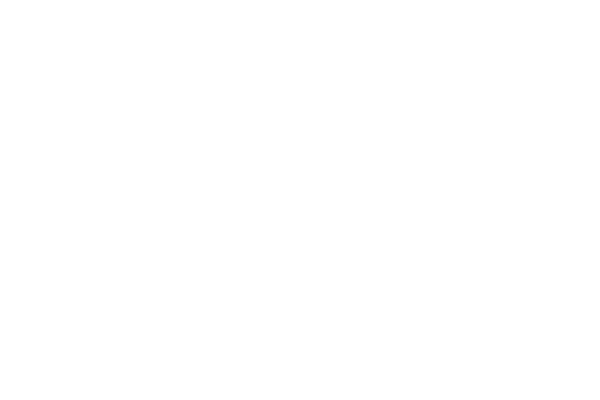
30ページ(全35ページ中)


