中津箒が復活するまで
2018.10.22
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
今回は「中津箒」の現在に至るまでの6代目代表の柳川直子さんの奮闘についてお話させて頂きます。
柳川家では代々箒屋を家業としてきましたが、直子さんが高校生の頃、時代の移り変わりと共に廃業をしてしまいます。
月日は経ち、かつての支店として残っていた京都の職人から、「正直、今までは商売として箒を作らされていた。そうではなく、これからは自分が納得する箒を作っていきたい」との事で直子さんは中津箒を復活させるべく、一念発起をします。
「かつて中津を支えてきたこの地場産業をこのまま廃れさせてはいけない!技術も受け継いでいかなければ職人さんも本当に居なくなってしまう!」
それから大学へ行き、芸術や文化について学んだり、日本や世界各国を渡り歩き箒の原料や知識について習得していきました。
まちづくり山上が運営する博物館、「市民蔵常右衛門」(しみんぐらつねえもん)には直子さんが集めた世界中の箒が展示されています。
その間、様々な方々との出会いもあり大学在学中に知り合ったのが、現在若手職人の1人として中津箒を支えている吉田慎司さんです。
吉田さんは2017年度LEXUS NEW TAKUMI PROJECT(レクサス匠プロジェクト)https://lexus.jp/brand/new-takumi/2017/の51人のうちの1人として神奈川県代表にも選ばれた方です。
次世代の箒の作り手は揃いました。が、今度は肝心の箒の材料になるホウキモロコシの確保に行き詰ります。
現在の箒の原料はほとんどが輸入品。今となっては国産のホウキモロコシはとても貴重だそうです。
しかし、しなやかで柔らかい箒を作るためにはなくてはならないもの。そこで、直子さんは材料から生産する事を決意します。
とはいえ、種をまき育て収穫することなど簡単ではありませんでした。
当時、種は農家にとってはお金より大事なもの。ホウキモロコシを育てているわずかな農家へ出向いたところですぐに分けてもらえるものではありませんでした。
3年ほど通いつめ、やっと手のひらほどの種を分けて頂き、そこから栽培を始めたのです。
現在では10ヘクタール以上の土地にたくさんのホウキモロコシが実るまでになりました。
次回は「箒のある生活」についてお話をさせて頂きます。
「中津箒ワークショップinカフェ豊作」
筒型小箒を作ります。※事前予約が必要となります。
日程:11月14日(水)
時間:①10:00~ / ②14:00~
場所:神奈川県愛甲郡愛川町半原482 カフェ豊作
申し込みTEL:0462803232(カフェ豊作)
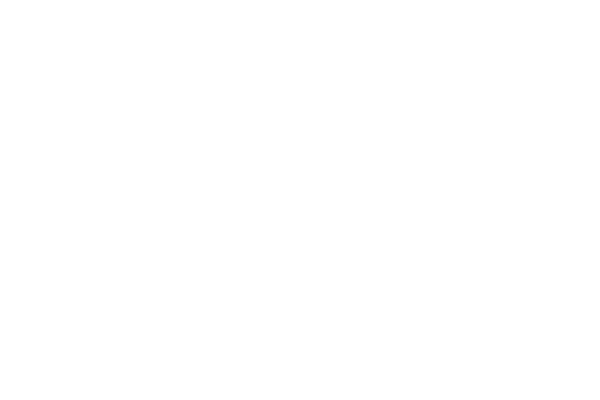
サーキット試乗研修会 in 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
2018.10.19
こんにちは 神奈川トヨタです。
今日は、袖ヶ浦フォレストレースウェイで行われた「社内研修」の様子をお届けします。
この研修は、86/BRZレースに参戦している「神奈川トヨタDTEC TEAM MASTER ONE」プロドライバーと「さなげアドベンチャーフィールド」のインストラクターの方々にもご協力頂き、“クルマの性能”など我々の商品の魅力体感するという内容で行われました。
まずは、「クラウン試乗プログラム」です。
コース上に設定された各セクションで「3.5HV」「2.5HV」「2.0ターボ」を乗り比べました。
ホームストレートでの圧倒的な「3.5HV」の加速性能に驚かされました。
次は、「タイヤ乗り比べ“86”試乗プログラム」です。
ここでは、86に3種類のタイヤを装着して試乗します。
体感したスタッフは「同じサイズなのにハンドルを切った時のグリップ感が全然違う!」「乗りはじめから違いが判る!」と、驚いていました。
そして、当社オリジナル商品「“DTEC ボディーダンパー”体感プログラム」では、ボディーダンパー装着済の新型クラウンを試乗しました。
新型クラウン用のボディーダンパーは、開発したばかりの新商品です。
開発スタッフも同乗しての試乗では、説得力のある話を聞くことが出来ました。
コース上では、凸凹路や速度域を設定したスラロームコース、高速コーナーでその機能の効果を実感しました。
ランドクルーザープラドの試乗プログラムは、大きな丸太を乗り越えるコースと階段昇りコースです。
搭載されている技術の高さに圧倒されました。
これは、アクティブトラクションコントロール体験シーンです。
アクティブトラクションコントロールとは、スリップを検知すると空転した車輪にブレーキをかけ、残りの車輪に駆動力を配分する機能です。
助手席側の後輪が空転してしまっていますが、慌てる必要はありません。
こんな時もグググッと力強く脱出してしまうのです。
日も落ち始めた最後には、協力頂いたプロドライバーによる同乗疑似レース体験です。
プロドライバーの運転を直に感じたスタッフは、みんな最高の笑顔で“86”から降りてきました。
今年の86BRZレースも残すところあと1レースとなりましたが、神奈川トヨタ一丸となって応援していきます。
皆様も応援の程、宜しくお願いします。
【ラウンド8】10/27 鈴鹿サーキット
https://toyotagazooracing.com/jp/86brz/
今回は、とても貴重な体験が出来た研修になりました。
このようなクルマの楽しさを皆さまにお伝えできるよう、今後も社内行事についてもご紹介していきたいと思います。
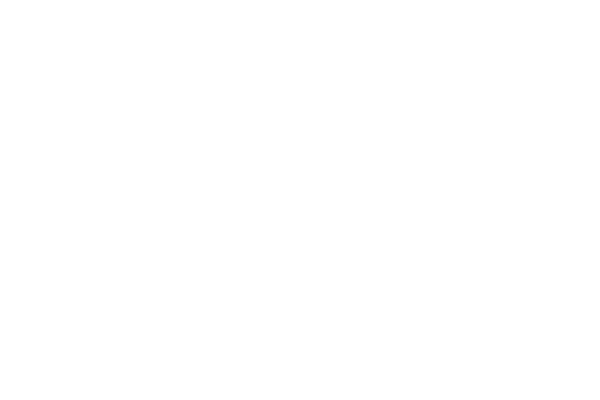
ショコラボさんがチョコレート販売会を行いました!
2018.10.19
こんにちは。
商品開発部ウェルキャブ室です。
10月17日に、横浜市都筑区にあるチョコレート工房ショコラボさんが、マイクスビル10階の社員食堂前で、販売会を行いました。
ショコラボさんは、一般社団法人AOHが運営する就労移行支援(一般型)です。
「健常者と障がい者の本当の意味のNormalization」をコンセプトとし、現実マーケットを意識しつつ、健常者と障がい者が共生・共働して商品づくりに取り組んでいます。
当社社員食堂前では、年に3回程度販売会を開いており、毎回楽しみにしている人もたくさんいるんですよ!
コンセプトもすばらしいですが、商品ラインナップもすばらしく、品数豊富で、大人向けのチョコレート、ワインなどお酒のおつまみにもなるものあります。
ウェルキャブ室は福祉車両を扱っている専門部署ですので、社会貢献を常に意識して業務に当たっています。
そのようなわけで、ショコラボさんと出会い、販売会を行うに至っているのです。
ショコラボさんのチョコレートは、オンラインショップのほか百貨店やホテルでも販売しています。
また、デビュー20周年を迎えたMISIAさんとのコラボ商品「ショコラdeメロンパンダ」は、オンラインショップやコンサート会場で数量限定にて販売しています。
ショコラボさん http://chocolabo.or.jp/
販売会の後には、販売スタッフの車好きのMさんが、2階ショールームで展示車に乗ったり、カタログを見たりして、楽しんでお帰りになりました。
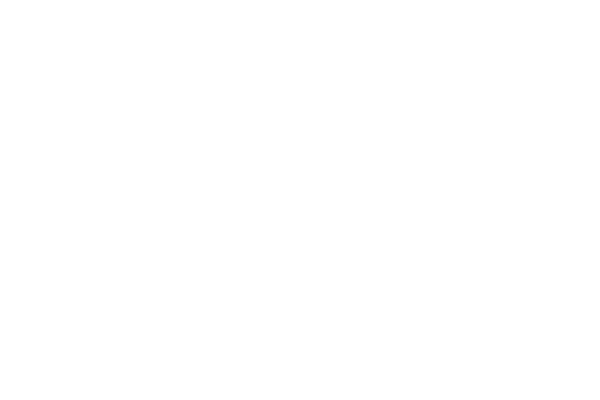
クラウン通がかよう 「ひゃくばん倶楽部」 第16話 : 観音開き
2018.10.16
“ひゃくばん倶楽部”へようこそ。私の名前は“ひゃくばん”。
この“ひゃくばん倶楽部”の案内人。一般的には、初代クラウンと呼ばれている。
「これ!“観音開き”のやつでしょ?」
私(初代クラウン)を見て開口一番、このように口にする年配の方は多い。
“観音開き”は、私の代名詞にもなっているが、どうしてそうなったのかを知る人は少ない。
そこで今日は“観音開き”の話をしよう。
私を開発するにあたって、担当者はまず販売店やタクシー会社をまわって、どんなクルマをつくったらよいかを聴いて歩いた。
ある時、タクシー会社の人がこんなことを言った。
「後ろのドアは、後方に開いた方が、開口部が広くなって乗り降りがしやすいんじゃないか?」
「ドアノブも中央にあった方が、お客様をお乗せする際に素早く操作できる!」
“ドアノブが中央にあると、素早く操作できる”ってどういうこと?と、思われる方も多いだろう。
今ではタクシーのドアは自動開閉があたりまえだが、当時のタクシーでは文字どおり助手席には助手が座っていて、お客様の乗降にあたっては助手が後部ドアの開閉を行っていたのだ。
こうしたタクシー会社の声が、私を“観音開き”にしたのだ。
ちなみに“観音開き”の初代クラウンは、1955年1月~1962年9月迄に116,400台生産されている。
二代目以降に観音開きが採用されなくなった理由は、「ライバル車との競争が激化し、綺麗なシルエットを重視したからだ」と言われているが、私は理由は一つじゃないと思っている。
二代目が登場する1960年代になると、日本も高速時代を迎えた。
“観音開き”は、後部ドアを半ドア状態で走行した場合、風にあおられて開いてしまう危険性があったのではないのだろうか。
色々な事情から“観音開き”はなくなってしまったが、今後も私の代名詞として語り継がれることは間違いないだろう。
それではまた、「ひゃくばん倶楽部」で逢おう。
■どうして私が、「ひゃくばん」と呼ばれているのか…ご存知ない方は「ひゃくばん物語」をご覧いただきたい。
【ひゃくばん物語】
私の名前は“ひゃくばん”。1955(昭和30)年生まれの63歳。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
「博物館でしかお目にかかれない」などという人もいるが、私は今でも地面さえあれば何処へでも走っていける。
もちろん、こうして今も元気に走り続けていられるのには理由がある…続きを読む
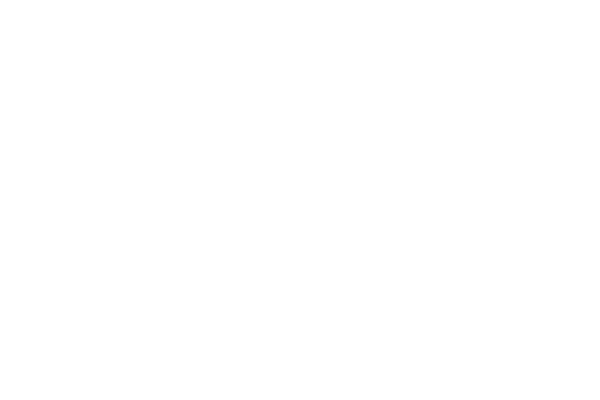
20ページ(全35ページ中)


