お茶の魅力を伝えるための授業
2018.10.15
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
以前、横浜とお茶の関係についてブログを書きました。
その際に、(株)栗田園の栗田様に取材をさせて頂き『ペットボトル飲料としてのお茶が普及し、急須を使って茶葉からお茶を淹れる習慣が少なくなっているという現状に危機感を感じている。自分の役割として本来のお茶の魅力を伝える活動をしていきたい』とお伺いしました。
その活動の一環として先日、栗田様が横浜市立義務教育学校西金沢学園中学部で講義を行いましたので、その様子についてお伝えします。
お茶の授業は「消費者経済学」という科目の一つとなっていました。
西金沢学園は小中一貫の学校で、今回は中学部の8年生。
つまり中学2年生の生徒さんが20名ほど参加です。
授業の内容は
お茶の美味しくなる淹れ方
お茶を実際に淹れてみよう
お茶の歴史や横浜との関係について
まずは栗田様から、煎茶と番茶の2種類のお茶の美味しい淹れ方を習います。
高級な茶葉ほどデリケートで、やはり淹れ方には基本があり、それを守ると本当に香りよく美味しい日本茶が淹れられるそうです。
最後の1滴が美味しいと、急須に残っているお茶を残すことなく湯呑に分けていきます。
お茶のプロが淹れたお茶を飲んでみたい~!!
と私は遠くから眺めていましたが、もちろんその試飲は生徒さん優先です(笑)
次は自分たちで淹れてみる番。
ポイントを押さえながら美味しいお茶を淹れられるでしょうか?
ぎこちないながらも、班の人数分のお茶をうまく分け「熱い~!!」とか叫びながらも「美味しい!!」とお茶を堪能していました。
生徒さん達が笑顔でお茶を囲んでいた様子を載せられずとても残念です。
ペットボトルのお茶では味わえない、淹れたてならではのお茶本来の香り・苦味・甘味を感じる事ができたのではないでしょうか?
何が何でも急須を使ってお茶を飲んで欲しい、ペットボトルのお茶はNO!ではありません。
日本には、平安時代から続く日本茶という素晴らしい飲み物があって、その魅力を忘れないで欲しい、という思いがこの授業には詰まっていました。
また“急須でお茶を淹れる→湯呑に分けて飲む”という事は、そこには自分以外の何人かが居るはずで、今淹れたお茶を同じ温度で「美味しいね、ほっとするね」と言える時間を共有できることなんだ、と思いました。
お茶を淹れるだけで、人が自然と集まり繋がりができ会話が生まれる。
大げさかもしれませんが、お茶にはそんな不思議な力があるのかもしれません。
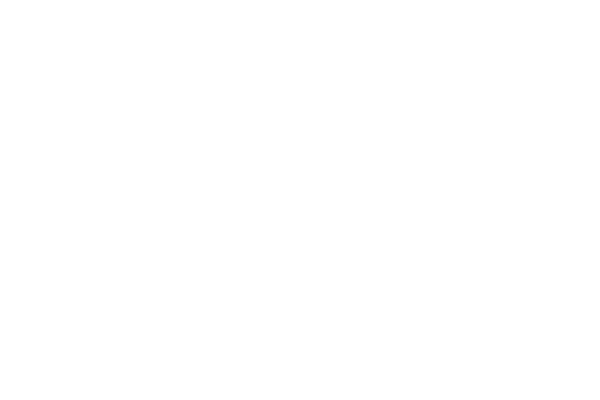
「THE GARDEN FESTIVAL 2018 vol.3」(ガーデンフェス)に参加しました!
2018.10.12
こんにちは!神奈川トヨタです。
今年で3回目となる「THE GARDEN FESTIVAL」(ガーデンフェス)が、10月7日、8日の2日間にわたり藤沢市にある辻堂海浜公園で開催されました。
神奈川トヨタは、初回から3年連続の参加です。
ガーデンフェスとは、海風が心地よい湘南の芝生の上で遊ぶフェスティバル。1年で最も気持ちの良い季節に芝生の上で、音楽と海風を感じながら美味しいものを味わい、人と人が繋がり、WORLD MUSIC / WORLD FOOD / CRAFT BEER / GREEN / CAFÉ / ART / MARCHEを多くの人が体感し共感する場として、2016年に誕生しました。≪ガーデンフェスHPはこちら≫
神奈川トヨタは、アウトドアショップmyX(マイクス)のグッズ販売ブースの他、今回の特別企画として、1959年製(59年前)のトラック「スタウト」を特別展示しました。
このスタウトは、県内で農業を営む方が所有していたワンオーナー車で、野菜を運ぶだけでなく、家族や友人との間に沢山の思い出をつくり、2005年の排気ガス規制により現役引退するまで大活躍しました。
その後、一度は博物館行きも計画されましたが、縁あって神奈川トヨタに寄贈され、「クルマがある暮らしの楽しさ、便利さ、うれしさ」を後世に伝える為の役目を担い、新車同様にレストアされました。
そして今も、ナンバープレートは販売当時の貴重な「神ナンバー」の為、フェス会場では、「すごいね、神戸から持ってきたんだ」と口にする方がとても多く、「正解は、神戸ではなく、神奈川の神です。」と言うやりとりが沢山ありました。
もう一つ多かったのが、ボンネットのトヨタエンブレムをみて、「すごーい!カタカナでトヨタだって。昔っぽいね!」とスマホでパシャっと撮影。
こうして、「来場者とのふれあい」のきっかけづくりに大活躍のスタウトでした。
オリジナルを忠実に再現したグリーンのボディーは、芝生の上で映え、フェスの雰囲気とマッチして人気の撮影スポットになり、足をとめて写真を撮る方も多く、お子さんを荷台に座らせて記念撮影する光景は、とても絵になりスタウトも喜んでいる様に見えました。
近くのブースで「10分で魔法をかけるプリンセスヘアアレンジ」をやっている美容師さんのグループがあり、アレンジを終えた子供たちもスタウトの前で記念撮影してくれるなど、思いがけないコラボ?も生まれて、ブースの周りは笑顔であふれていました。
こうして、2日間にわたって沢山の方々にスタウトを見て頂き、また、スタウトを通じて色々な方とお話しすることができました。日比谷で行われた最初のモーターショーを思い出し、懐かしんでいた御年配の男性。
旧車好きで、ご自身が所有するMGのことを楽しそうに話していたご夫婦。クルマはこれくらいシンプルなのが良いのよ!と仰っていた犬をつれた女性。
そして、「神奈川トヨタさんは、良いことしてるね!さすがだね。」とお褒めの言葉。これは、最高に嬉しかったです。
ガーデンフェスに来場された方たちが、「自然や音楽を家族や仲間と楽しむ」という文化を体感し、スタウトの展示を通じて、「大切なものを未来につなぐことで生まれる感動、クルマから連想するワクワク感」を感じて頂けたのではないでしょうか。
最後に、このフェスへの参加とスタウトの展示に協力して下さった実行委員の皆様、そして、マナーやエチケットを守ってスタウトをご覧になって頂いた来場者の皆様へ感謝申し上げます。
皆様、今年もありがとうございました!そして、お疲れ様でした!!
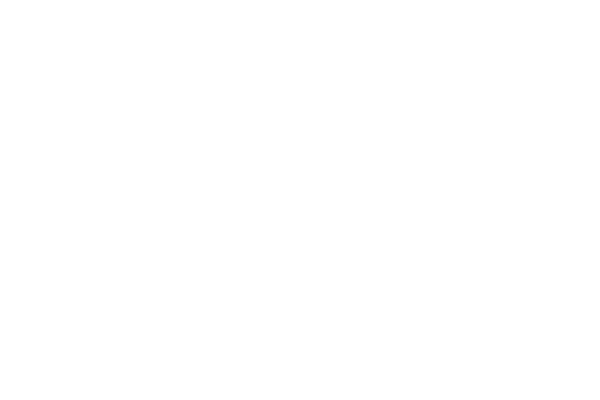
箒(ほうき)でゴミを自然に返す
2018.10.08
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
神奈川県は「神奈川プラごみゼロ宣言」を発表しました。
2030年までに、プラスチック製ストローやレジ袋の利用廃止・回収を目指す、というものです。
便利なものを今更やめる、というのは簡単な事ではありませんが、便利さと引き換えに失った大切なものを、また取り戻すチャンスと考えられたらいいのかな、と思いました。
今回はcafe豊作さんの輪から広がった「中津箒(ほうき)」についてお話します。
箒(ほうき)と聞くと学校の掃除の時に使っていたT字のものや、落ち葉をかき集めるものを思い出し、懐かしい気持ちになります。
ご紹介する箒は「座敷箒」といい、主に畳の部屋のゴミを掃除するものです。
日本の昔の家屋は畳や板の間を可動式の襖や障子で仕切った開放的な造りで、テーブルのような動かしにくい家具や動かせない壁はあまりなかったので、掃除には箒が最適でした。
ゴミも、せいぜい砂ぼこりや綿ぼこり・髪の毛などだったので、掃き出し窓から箒で掃き家に入ってきたゴミを“自然に返す”ことで十分だったのです。
時代は進み、家自体の造りや暮らし方、気候などが変わり、掃除の仕方も変わりました。
電化製品の登場により、箒を使う家が少なくなったのです。
また、もともと中津(旧中津村)では箒産業が盛んでしたが、家業として箒を作る担い手が減少していき、現在ではかつての職人も高齢でごくわずかとなってしまいました。
そこで(株)まちづくり山上では、箒づくりの復興を目指して「中津箒」を立ち上げます。
かつての箒製造卸の6代目代表の柳川直子さんは若手の職人の育成に尽力を注いだり、箒の魅力を知って頂く活動を積極的にされております。
次回は、現在に至るまでの6代目代表の柳川直子さんの奮闘についてお話させて頂きます。
(株)まちづくり山上 HPはこちら
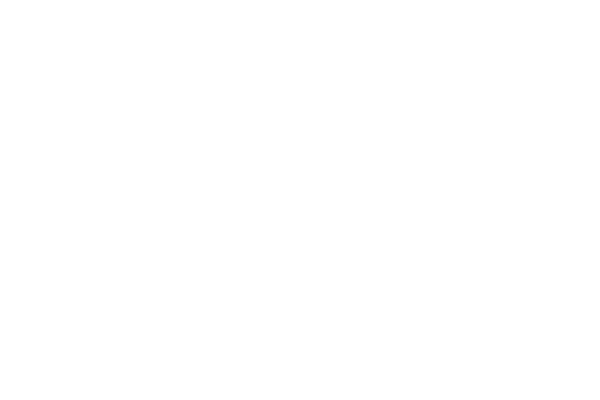
クラウン通がかよう 「ひゃくばん倶楽部」 第15話 : 中柱
2018.10.04
「ひゃくばん倶楽部」へようこそ。私の名前は「ひゃくばん」。
この「ひゃくばん倶楽部」の案内人。一般的には、初代クラウンと呼ばれている。
神奈川トヨタのショールームで巡回展示をしている時のことである。
私(初代クラウン)の正面に立って、じっくりと眺めていたご年配のお客様が腕組みをして首をかしげた。
「これはホントの初代クラウンじゃないな?」
トヨタ博物館の初代クラウンはフロントウィンドウが2枚のガラスで中柱があるのに、神奈川トヨタの初代クラウンは1枚のガラスで中柱がない。
これは初代とはいえない、とおっしゃったのだ。
それを聞いたスタッフは「これのことですね。」と、トランクからフロントウインドウの中柱(センターピラー)を取り出してみせた。
「そうこれ!これがなきゃ初代クラウンじゃない。」
お客様のご指摘の通り、初代クラウンが発売された1955年の1月には、曲面ガラスの形成技術が完成していなかったので、中柱の入った2枚ガラスが採用されていた。
同じ年の12月にクラウンデラックスが発売になるとフロント・ウインドウが1枚ガラスになり、これを見た私のご主人は、視界が良くなるからとガラスを交換していたのだ。
その時、捨てられずに残しておいたのがこの中柱だった。
スタッフの説明にお客様もご納得され、そのうえで現在も走り続けている私を褒め称えてくれた。
少し、誇らしげな気分になった私がいたのは言うまでもない。
それではまた、「ひゃくばん倶楽部」で逢おう。
■どうして私が、「ひゃくばん」と呼ばれているのか…ご存知ない方は「ひゃくばん物語」をご覧いただきたい。
【ひゃくばん物語】
私の名前は“ひゃくばん”。1955(昭和30)年生まれの63歳。一般的には初代クラウンと呼ばれている。
「博物館でしかお目にかかれない」などという人もいるが、私は今でも地面さえあれば何処へでも走っていける。
もちろん、こうして今も元気に走り続けていられるのには理由がある…続きを読む
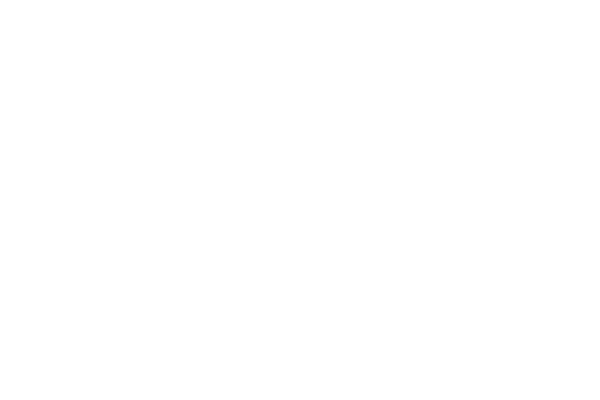
21ページ(全35ページ中)


