茶箱絵【第5話】
2018.08.27
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
8月もあとわずかなのに、まだ暑い!!秋恋し・・・
ところで「横浜とお茶の関係」の回で、横浜開港当時はお茶の輸出が盛んだった
というお話をしました。
当時、お茶は「茶箱」という湿気に強い木箱に入れられ外国へ輸出されていました。
その茶箱に貼ったラベルの事を「茶箱絵」と言います。
品質・銘柄・商館名が分かるようにするため、また港の作業員が積荷を一目で判断できるようにするために、貿易を行う外国の商人がラベルを必要としたそうです
印刷だとインクの匂いがお茶に移ってしまうため、この茶箱絵には木版画摺りの技術が用いられていました。
それぞれの茶商が工夫をこらし、お茶の味だけでなく、茶箱絵のデザイン性も競っていたようです。
茶箱絵に描かれているアルファベット文字の事を蘭字と言います。
英単語を知らない当時の浮世絵師が見よう見まねで書いたためか、独特な雰囲気があります。
またお茶をその出来によってランク付けしていました。
1等「チョイヲイスチス」
2等「チョイヲス」
3等「フェンチース」
4等「フェン」
5等「クルミリン」
6等「ミリン」
?????
これは茶箱絵を描いていた英語を知らない浮世絵師が、外国人が話す発音をそのまま
聞き取り使っていたようです。
正しくは、
チョイオイスチス → Choicest
チョイヲス → Choice
フェンチース → Finest
フェン → Fine
クルミリン → Good Medium
ミリン → Medium
茶箱絵の中にも、“EXTRA CHOICEST”や“CHOICEST”の文字が描かれています。
他にも
①の“SUNDRIED”は仕上げの段階で再火入れを鉄釜を用いた
④の“PORCELAIN FIRED”は陶磁器で炒って乾燥させた
⑤⑥の“UNCOLORED”は着色なし “MAY PICKINGS”は“5月に摘まれた”
という意味だそうです。
YOKOHAMAの文字もところどころに見えますね!
このようなカラフルでモダンなデザインの絵が描かれた茶箱が、横浜港で行き交う情景を想像するだけで、当時の活気ある姿が思い出されますし、今となっては本当に不思議な感じがします。
残念ながら、茶箱絵は輸出される木箱に貼られていたため、そのほとんどが外国へ渡ってしまいました。日本には現存するものが少ないそうです。
デザイン性の高さから大変評価が高く人気で、外国では現在でも高値で取引されているそうです。
こんなに素敵な茶箱絵、実際に見てみたいと思いませんか?
実はこの希少な茶箱絵を扱った展示会が来年開催されます!!
「時代を彩るグラフィック・デザイン - 蘭字から昭和モダンへ -」
2019年3月16日(土)~5月19日(日)
https://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/pdf/info2018.pdf
フェルケール博物館
http://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/index.html
静岡市清水区港町2-8-11
電話 054-352-8060
開館時間 9:30~16:30
休館日 月曜(但し祝祭日・振替休日の場合は開館)
入館料 大人400円・中高生300円・小学生200円※毎週土曜日は小中学生無料
JR清水駅または静鉄新清水駅より、 静鉄バス「フェルケール博物館」下車
駐車場無料駐車場あり(大型バス不可)
茶箱絵の他に、横浜から輸出された生糸ラベルやせっけんのパッケージなども展示されるそうです。
お時間がある方は、その当時のモダンなデザインの世界に浸ってみてはいかがでしょうか?
次回は「お茶の値段のちがい」についてお話させて頂きます。
※ブログアイキャッチ画像、ブログ内の画像 日本茶業中央会 提供
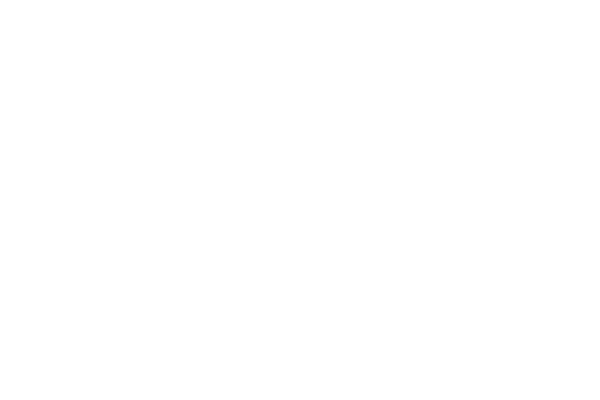
ユニバーサルデザインタクシー試乗会
2018.08.21
こんにちは、神奈川トヨタ法人タクシー室です!
先日、ユニバーサルデザインタクシー試乗会*が開催されました。
*主催:認定NPO法人かながわ福祉移動サービス、ネットワーク協力:関東運輸局 神奈川運輸支局
県内の特別支援学級や養護学校、障がい福祉、介護保険事業所、市民活動団体、横浜市障がい福祉課、都市交通課、国交省関東運輸局、タクシー協会などたくさんの関係各所が参加。
さらに自動車メーカーの日産・トヨタや販売会社も加わり、ユニバーサルデザインタクシーへの意見や乗車した感想など、熱い議論 が交わされました。
当日は、とてもとても暑い日で、皆で熱い議論を交わし、皆さんの厚い心で今後のタクシーを作り上げていく貴重な時間となりました。
これからも神奈川トヨタは販売のみならず、様々な機会を活用し社会貢献に繋がる活動にも力を入れて参ります!
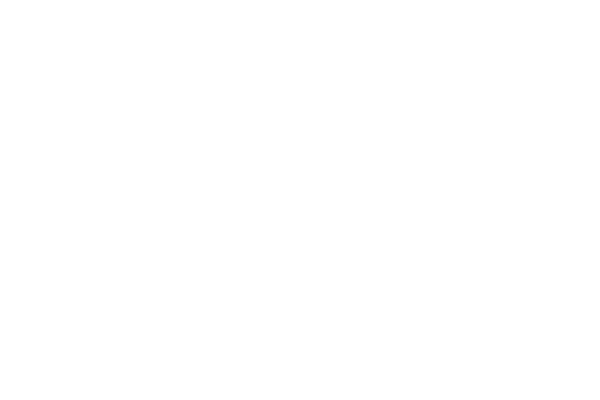
お茶は飲む×食べる!【第4話】
2018.08.20
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県”」のウッチです!
夏休みが終わってしまい(泣)冬休みまで長いな~なんてすでに思っています。
突然ですが、お茶は飲むものではなく、食べるものだと知っていましたか?
これも栗田園さんから聞いたお話です。
とは言っても、茶葉をむしゃむしゃ食べる訳ではありません。
急須で淹れたお茶は、最後に湯呑の底に緑色の茶殻が残ります。
実はあの茶殻にこそ体にいい成分がたくさん含まれているのです。
わたしたちが飲んでいる液体部分にはお茶の成分が20~30%くらいしか染み出して
いないそうです。
日本茶の効果として、虫歯と口臭予防、食中毒予防、糖尿病やがんの予防、老化防止効果
などが挙げられます。
例えば、食中毒の40%を占める腸炎ビブリオ菌は、お茶に出会うと死んでしまうそう。
こんな素晴らしい効果のある茶殻を飲み残しては本当にもったいない!
湯呑を回し、茶殻を上澄みのお茶と混ぜ、濁らせて「食べながら飲む」のが本来の
飲み方なのです。
実は昔は茶葉をむしゃむしゃ食べていたそうで、最近では茶葉を使った料理レシピも
数多くあります。
例えば、「茶殻のふりかけ」
1.茶殻を電子レンジで乾燥させ、ミキサーで細かくし、フライパンで炒る
2.フライパンに塩、桜海老、じゃこ、たらこ、白ごま等を加え水分が無くなるまで炒る
今の季節、おにぎりに混ぜれば食中毒の予防にもなります。
本来のお茶の効果や味を楽しむためにも、茶葉から入れた、茶殻も取れる濁りのあるお茶を飲むことをお勧めします。
次回は「茶箱絵」についてご案内させて頂きます。
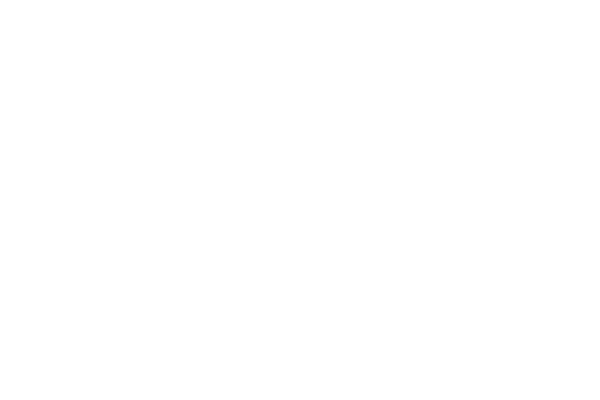
栗田園さんに伺ったお話“中国の緑茶は透明に近い?”【第3話】
2018.08.13
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
今、夏休みで東北に来ておりますが、全然涼しくありません…。
残念ながら、避暑地と呼ばれる楽園は日本にはもう無いのかもしれません。
ところで、お茶の老舗 栗田園への取材で
「中国にも緑茶があるんだけど、色が薄いんだよ」という事を聞き、
日本茶は深い緑色をしているのに何が違うのだろう?と興味を持ちました。
今回はそのことについて私なりに調べた事をお話させて頂きます。
中国茶というとウーロン茶を思い浮かべるかもしれませんが、“緑茶(リュウチャ)”と
呼ばれるものがあり、実は中国で飲まれている中国茶消費量の80%を占めているそうです。
茶葉は、摘んだ瞬間から酸化酵素の働きによって発酵が始まります。
日本茶は摘んですぐ茶園の近辺で蒸すことで酸化酵素の活性を止め、鮮やかな緑色を
保ったままで流通しています。
一方、中国茶の場合、国土が広く茶葉を運ぶ時間がかかってしまう、茶園近くで熱処理が
できない、という理由で発酵が進んでしまい、緑色の成分である葉緑素(クロロフィル)が壊れてしまうそうです。
そのため、中国の緑茶は沸かすとほとんど透明に近い緑色をしています。
日本茶は苦味や旨味成分が壊れていないため、お茶本来の「味」を楽しめます。
一方、中国茶は酸素とお茶の成分が多く交わることで作られる「香り」を楽しむことが
できるのです。
元々の茶葉が同じでも、国土の特徴や茶葉の扱い方に違いがあるからこそ、出来上がるお茶に違いが生まれ、楽しみ方が広がるんですね。
神奈川県にはこの中国茶が手軽に手に入る場所があります!そう横浜中華街!
普段から飲みなれている日本茶と中国茶との味や香りのちがいを楽しむ、という
優雅な時間をたまには過ごしてみてはいかがでしょうか?
左:日本のお茶 右:中国のお茶
次回は「お茶は飲むものではなく、食べるもの?!」をご案内させて頂きます。
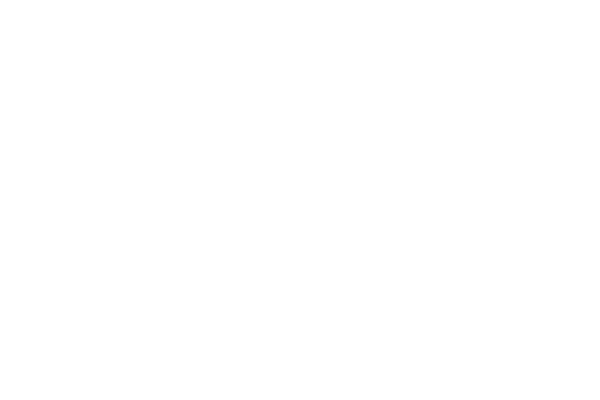
26ページ(全35ページ中)


