森のハーモニー 第7話 「エコぞうり」
2019.05.22
こんにちは。
僕は2001年1月30日の第6回プリウス森木会である夫婦により作られたウッドクラフトのキリンです。
今日は「エコ草履」づくり講習会のお話をしようと思います。
2000年2月に30周年を迎えた神奈川トヨタ保土ヶ谷店は、お客様の日頃のご愛顧に感謝し、『神奈川トヨタ保土ヶ谷店 30周年ふれあい感謝祭』を開催しました。
バナナのたたき売りなどのお楽しみ企画に加え、地域の皆さんと一緒に身近な環境保護に取り組もうと「エコ草履づくり講習会」を開催しました。
エコ草履とは古布を再利用して、ワラ草履の要領で作る室内履きのことです。
講師の先生(写真中央)は、古布や古着などの古繊維を回収し、リサイクルする活動を行っているファイバー リサイクル ネットワークから来ていただきました。
この「エコ草履」は環境にやさしいだけではありません。
夏は汗を吸い、冬は暖かく、足裏をほどよく刺激してくれるので履き心地も良く、さらに室内を歩けば床のホコリをふき取ってくれる、まさに優れものなのです。
参加していただいたお客様も説明を受け、ぜひ使ってみたい!と喜んで作っていました。
神奈川トヨタは80年の歴史の中で、様々な環境保護活動を地域の皆さんと一緒に取り組んでいるんですね。
世の中にはお金では手に入れられない「もの」があります。
自らが手足を動かし、やっと手に入れる「もの」。
こうして手に入れた「もの」には特別な思い入れが生まれます。
僕もそのうちの一つだといいな。
それでは、僕はそろそろお家に帰ります。
話をきいてくれてありがとうございました。
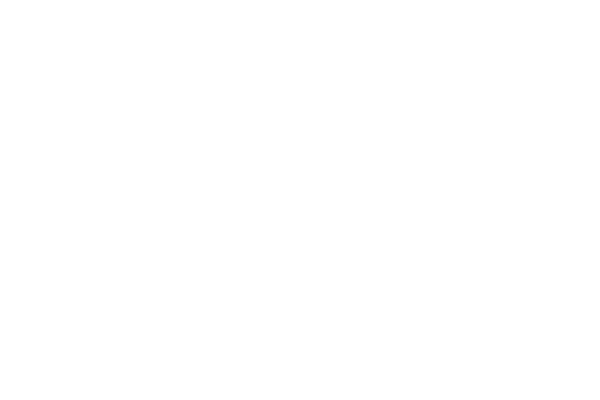
世界農業遺産 静岡の “茶草場農法”
2019.05.21
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
最近は天候が悪い日も多くなり、梅雨が近づいているのかな~など、少し憂鬱な気分になっています。
とはいえ、この雨が降らないと作物も育ちません。
恵みの雨と思い、少しの期間は我慢して今年買ったレイングッズを楽しもうと思います。
ところで「世界農業遺産」をご存じでしょうか?
「世界農業遺産」は、食料の安定確保を目指す国際組織によって2002年に創設されました。
地域環境を活かした伝統的農法や生物多様性、農村文化、農村景観を守る土地利用などを次世代に継承していくことを目的としています。
「世界遺産」との違いは、保護する対象が、遺跡や歴史的建造物・自然という“不動産”であるのに対し、「世界農業遺産」は“農業のシステム”を認定し保全している、という点です。
世界では21ヶ国、57地域、日本では11地域が認定を受けています。
2013年5月、良いお茶を作ろうとする農家の営みと、生物多様性の確保を両立する農法が評価され、静岡県の“茶草場農法”が認定されました。
このような農法があるという事、この農法を守り続けている農家の方々がいらっしゃるという事、この農法が国際的に認められたという事を初めて知り、私は日本人としてとても誇らしくなりました。
重労働で手間暇がかかるにも関わらず、それでも伝統的な農法を守り続ける茶農家の方々の大変な努力と、美味しいお茶を作りたい、届けたいという思い、また、美味しいお茶を育てる環境や生き物たちを守り続けたいという気持ちを強く感じました。
今回はこの「茶草場農法」についてお伝えします。
茶草場(ちゃぐさば)とは、茶畑の近くにあるススキやササなどが生えた草地の事で、茶草場農法とは、その茶草場の草木を有機肥料として利用する農法です。
茶園にある茶草場
茶園周辺の茶草場
刈り干ししているススキやササ
干したススキやササを敷いた茶園
(掛川市役所ホームページから引用)
効果としては
・夏は保湿、冬は保温効果が期待できる
・雑草を生えにくくする
・草が分解され土に戻ることで、堆肥となる
など多くの利点をもたらし、良質な土壌を作り出します。
その土壌で育った茶は味や香りが格段に良くなるそうです。
茶草場は放っておくと、単なる雑草地になってしまいます。
通常、草刈りは、大きく成長する梅雨前に行いますが、茶草場では夏に成長した草花が種を落とす秋から冬にかけて草刈りをします。
この作業をすることで、春を迎えた時、まっさらに刈り取られた地表に光がしっかりと当たり、新たな植物が芽を出します。
このように人の手が加わった草地を「半自然草地」と言い、昔は日本中どこでも見られました。
しかし農業や人々の生活が近代化され、手間暇かけ草木を肥料として使う事が少なくなり多くの半自然草地とともに、そこを住みかとしていた貴重な動植物が姿を消しました。
そのような中でも静岡の茶農家の方々は、茶の品質向上や草地の環境を守るために茶草場を維持・管理してきたのです。
茶畑だけでなく、茶草場まで人の手で維持・管理する事は容易ではなく、大変なご苦労があることでしょう。
静岡県のお茶が特別に美味しい理由が少しでも分かった気がしました。
丸山製茶に伺った際、丸山社長がその場でブレンドをし、真空パックにしてくれた新茶を飲むのを楽しみにしていましたが、茶草場農法の事を調べるにつれ、その重みを感じ、なんだかもったいなくて、まだ飲むことができていません。
次回は摘まれた茶葉がどのようにして私たちが目にする商品になるのか、についてお届けします。
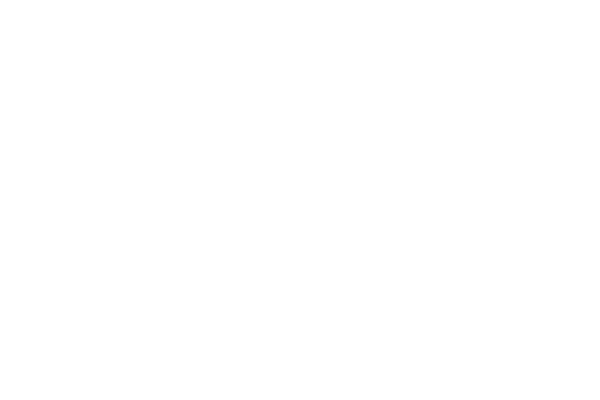
森のハーモニー第6話「ころもがえ」
2019.05.15
こんにちは。
僕は2001年1月30日の第6回プリウス森木会である夫婦により作られたウッドクラフトのキリンです。
寒暖の差が激しい日々が続いていますが、さすがに厚手のコートなどは着る機会がなくなってきましたね。
お気に入りの冬着はクリーニングを済ませて、クローゼットで「令和」の秋を待ってもらいましょう。
ところで、皆さんは何年も袖を通していない衣類はありませんか?
最近は衣類をインターネットなどで売る、という手段もあるようですが、まだまだゴミとして捨てられてしまうケースも多いようです。
でも、衣類などの繊維は、ほぼ100%リサイクルが可能だと言われています。
そこで、1992年に横浜市中区を本拠地とする市民ボランティアグループが、「市民の手で古着を回収し、リサイクルのルートにのせる仕組みを作ろう」と、『ファイバー・リサイクル・ネットワーク』という団体を立ち上げました。
トヨタのお店と何の関係があるの?と思われるかもしれませんが、実は神奈川トヨタもこの回収活動に参加していたんです。
きっかけは、カレリア本牧(現在は中店に統合)が発行していた情報誌。
地域ボランティア欄にこの活動を紹介したところ、回収拠点になってほしいとの要望を受け、お店に回収所を設置していました。
残念ながら、現在は店舗の移転・統合により回収拠点としての活動は休止していますが、ファイバー・リサイクル・ネットワーク』は横浜市南区に移転し、活動を継続しています。
回収された「古布・古着」はそのまま海外輸出されたり、工場用雑巾として使われたり、繊維に再生して使われたり…と様々。
僕も間伐された木から生まれ変わって大切にされているので、回収された布も新しく生まれ変わって大切にされているといいな、と思います。
…これはプリウス森木会が発足する2年前の話。
神奈川トヨタは80年の歴史の中で、様々な環境保護活動を地域の皆さんといっしょに取り組んできたんですね。
それでは、僕はそろそろお家に帰ります。
話をきいてくれてありがとうございました。
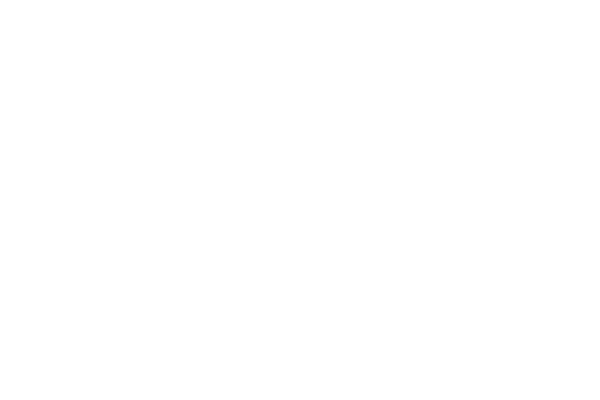
新芽育つ、静岡県掛川市の茶畑に行ってきました!!
2019.05.08
こんにちは!
ブログ「神奈川 大好き!だって“生まれも育ちも働く場所も神奈川県」のウッチです!
5月に入ったというのに、最近は雨や寒い日が続いております。
先日見学してきた静岡県の茶畑の新芽が低い気温にやられてしまっていないか・・・
と心配するばかりです。
なぜこんな気持ちになっているのか?
茶畑に実際に行った様子と合わせてお伝えします。
4月23日 栗田園様とお取引がある、掛川市の丸山製茶株式会社様を尋ねました。
丸山製茶は創業が昭和8年。
“深蒸し”を特徴とする掛川茶で有名な掛川市を代表する製茶の会社です。
快く取材を受けてくださった丸山製茶の丸山社長が茶畑を案内してくださいました。
幹線道路沿いから少し山の方へ入っただけで、すぐに茶畑が出現!!
茶畑の間の道を縫うように車で進むだけで、緑色の迷路の中を彷徨っているようでした
当日はあいにくの雨で、品質が落ちる事から茶摘みは行われていませんでした。
どこを見回しても、鮮やかな緑の新芽を付けたお茶のじゅうたんが広がります。
雨が少し止み、茶葉と雨が混ざった爽やかな香りと、いつもよりはっきりと聴こえる
鳥の鳴き声が本当に心地よく何度も深呼吸をしました。
茶畑の中に立っている電柱のようなものは、「防霜ファン」だと
教えてくれました。
「霜を防ぐために、空気を混ぜるんだろうな~、でもなんであんな高いところから?!
もっと背を低くして茶葉の近いところから空気を当てればいいのに。」
と不思議に思いました。
実は地面に近いところには冷たい空気の層があり、そのままだと霜ができやすくなります。
茶葉の新芽は霜害に遭うと、細胞が破壊され枯死してしまいます。
逆に地上3~5mには温かい空気の層があり、その空気を上から茶葉の方へ送り込むこと
で空気を撹拌し、霜の被害を防いでいます。
(中央に見える地肌が見えている部分は、茶の木を植えたばかりの畑)
それでも標高が高いところにある茶畑の新芽は、気温が低いため寒さの影響を受けやすく、
霜の被害を受けないよう、大変苦労されている、との事でした。
そんな中でも青々とした新芽はたくましく活き活きと育っており、摘んでもらえるのを
今かと待っているよう。
場所によっては、新芽がすでに摘まれている茶畑もありました。
これは生育状況の違いではなく、早生と晩生というように品種を分けて植える事で
収穫時期をずらしているとの事でした。
自然が相手のため、大変なご苦労がありつつも、様々な工夫をしながら大切な茶葉を
守っている様子がうかがえました。
そんな自然と上手く付き合い、環境を守りつつも、より良質なお茶を生産しようとする
茶農家の方々の努力が高く評価された活動があります。
その活動の一つとして次回は世界農業遺産に認定された掛川市の「茶草場農法」について
お伝えします。
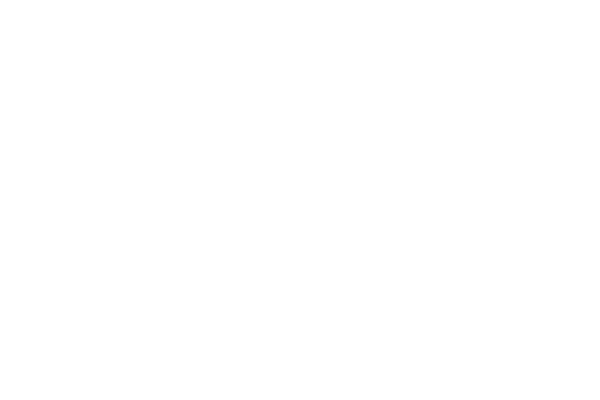
3ページ(全34ページ中)


